私はふだん、AIツールを紹介・解説するサイトを運営しています。日々さまざまな生成AIを試しては、「これはどんなことに使えるか?」「どこまで実用的か?」を探るのがライフワークのようになっています。
そんな中で、ひとつの実験として「ChatGPTにライトノベルを書かせてみる」という試みにチャレンジしてみました。
約1カ月間、毎日のように試行錯誤を重ねながら、AIに小説を書かせては調整を繰り返し、シリーズとしての形になるよう制作を続けました。
完成した小説は、人気投稿サイト「小説家になろう」にて実際に公開。基本的にはAIが生成したテキストを100%そのまま使い、筆者は誤字脱字や細かな違和感を軽く修正した程度です。
結果としては、「上手くいかなかった」というより、「AIに100%クリエイションを任せるのは、今はまだ無理だな」と痛感する体験となりました。
本記事では、その理由や背景を具体的に振り返ってみたいと思います。
理由1:AIが小説の設定を覚えていられない
今回作っていたのは、いわゆるファンタジー系のライトノベルでした。
ラノベにありがちな、街や王国の設定、魔法やモンスターの仕組み、登場キャラクターたちのバックグラウンドや性格など、ある程度しっかりとした世界観が必要なジャンルです。
そのため、最初に舞台や設定、キャラの関係性などをプロンプトでしっかり定義してから、物語を書かせていました。1話単位で見ると、AIはその都度きちんと設定に沿った内容を出力してくれます。
ところが、物語が数話進むと、AIは自分で出力した設定を少しずつ忘れてしまうのです。
たとえば、数話前に訪れた町にキャラクターたちが再び戻ってくるシーンでは、町の特徴や名前がまるで別の場所のように描かれていたり、以前に使っていた魔法の効果や名称が変わっていたり、キャラクターに与えていたはずの小目標が、別の目的にすり替わっていたりといったズレが頻繁に発生しました。
こうしたズレをAIに指摘すると、一応その箇所だけを修正してくれるのですが、それが逆に整合性を崩す原因にもなります。話の流れに無理が出たり、辻褄合わせが不自然になったりして、物語全体がちぐはぐな印象に。 この問題は「プロットや設定を人間が常に管理・補正しながら進行する」ことで改善できますが、そうすると今度は「100%AI任せ」というコンセプト自体が崩れてしまいます。
つまり、人間がいないと破綻してしまう時点で、“完全自動”はまだまだ難しいのだと実感しました。
理由2:キャラクターの口調や語尾がブレる
1つ目の「設定が覚えられない問題」とも関連するのですが、キャラクターの“しゃべり方”にも安定性のなさが目立ちました。
たとえば、女の子キャラが突然「俺」と自称し始めたり、男性キャラが急に女言葉で話し出したりと、明らかに違和感のあるセリフが出てくることが多々ありました。しかも厄介なのは、それが初期からブレているのではなく、「数話前までは問題なく喋れていたキャラが、ある日急に変わってしまう」というパターンが非常に多いという点です。
また、ラノベらしくアニメ風の特徴的な語尾(例:「〜なのです!」「〜っス!」など)を使うキャラも登場させていたのですが、そうした個性的な口調も話数が進むにつれて徐々に曖昧になり、いつの間にか普通のしゃべり方に変わってしまっていることもよくありました。
このような“話し方の一貫性”は、キャラクターの魅力を支える非常に重要な要素です。読者は、キャラの個性や関係性に引かれて物語を読み進めるものなので、ここがブレてしまうと一気に没入感が失われます。 もちろん、セリフ回しや語尾を人間が都度修正すれば解決できます。しかし、それはやはり「AIがすべてを書いた」とは言えず、当初の“100%AI任せ”という実験の趣旨からは外れてしまう結果になります。
理由3:ストーリーやキャラクターが浅く、心に響かない
(※これが最も大きな問題だった)
「こういう感じのラノベを書いて」とChatGPTに指示すれば、一応それなりのプロットと設定を持った物語を生成してくれます。世界観や登場人物も一通りそろっていて、文章としても一見まとまっているように見えます。
しかし、読み進めるうちに、どうにも物語に引き込まれない。
設定や展開はあるのに、“面白くない”のです。
なぜか?その一番の理由は、物語に熱量がないからだと思います。
AIは、「こういう世界を描きたい」「こういうシーンを絶対に入れたい」「このキャラにこんなセリフを言わせたい」といった書き手としての情熱や執念を持っていません。あくまで過去に学習したデータをもとに、“それっぽいもの”を生成しているだけです。
そのため、出来上がる物語はどこかで見たような平均的なストーリー、無難な構成、予定調和の展開になりがちです。
さらに深刻なのが、キャラクターの浅さです。
AIが作るキャラは、設定としては存在していても、行動やセリフに人間らしい揺れや葛藤、感情の起伏がほとんどありません。結果として、どこかロボット的で、読んでいても心が動かされるようなキャラにはなりにくいのです。
たとえば「表では強がっているけど、内心は怯えている」「嫌いな相手に対して思わず優しさが出てしまう」といった感情の複雑さや矛盾は、人間が意図して書くからこそ生まれるもの。AIは、そうした“矛盾の中にあるリアル”を描くのがとても苦手です。
個人的には、この“物語とキャラの浅さ”こそが、AIに完全に小説を書かせるうえで最大の壁だと感じました。
完全自動の創作に挑戦して見えた“壁”
以上の3つの理由から、現時点ではAIに100%小説を書かせる=クリエイションを完全に任せるというのは、やはり現実的ではないと感じました。
設定の記憶が曖昧で、物語の整合性が崩れやすい。
キャラクターの口調や個性が安定せず、魅力が薄れてしまう。
そして何より、物語やキャラに込められるべき“熱量”や“人間らしい複雑さ”がないことで、ストーリー全体が平板で心に残りにくくなってしまう。
文章を生成するという作業自体はAIにできても、そこに魂を宿す“創作”というレベルにまで到達するには、まだ大きな壁がある──そんなことを強く実感した一カ月間のチャレンジでした。
では、AIは創作において無価値なのか?
とはいえ、「だからAIは創作には使えない」と結論づけたいわけではありません。
むしろ、“創作をしたい人間”がAIをうまく使えば、十分に力強い相棒になり得ると感じています。
たとえば小説において、合戦シーンを書く際に「実際の戦いはどんな流れで進むのか?」「馬や装備はどう配置すれば自然か?」「城の構造や材質は?」といった技術的・背景的な要素を補うことは、AIが得意とするところです。
物語の中で必要になる細かいリアリティを補強するためのリサーチや描写支援には、かなり頼れる存在です。
絵においても同様で、メインとなるキャラクターやストーリーラインは人間のクリエイターが担いながら、手間のかかる背景描写だけをAIに任せるといった活用方法も現実的です。
こうした“分業”によって、作業の効率化や完成度の底上げは十分可能です。
また、そもそも「物語を作ってみたい」「絵を描いてみたい」と思っても、スキルがなくて踏み出せなかった人にとって、AIはその最初の一歩を支えてくれる存在にもなります。
要するに──
クリエイションに対して熱量を持っている人の“手助け”としてのAIであれば、今の段階でも十分活用できるし、大きな可能性を秘めていると思います。
ちなみに、
以下が実際にAIに書かせて投稿した作品です。興味のある方はぜひ読んでみてください。


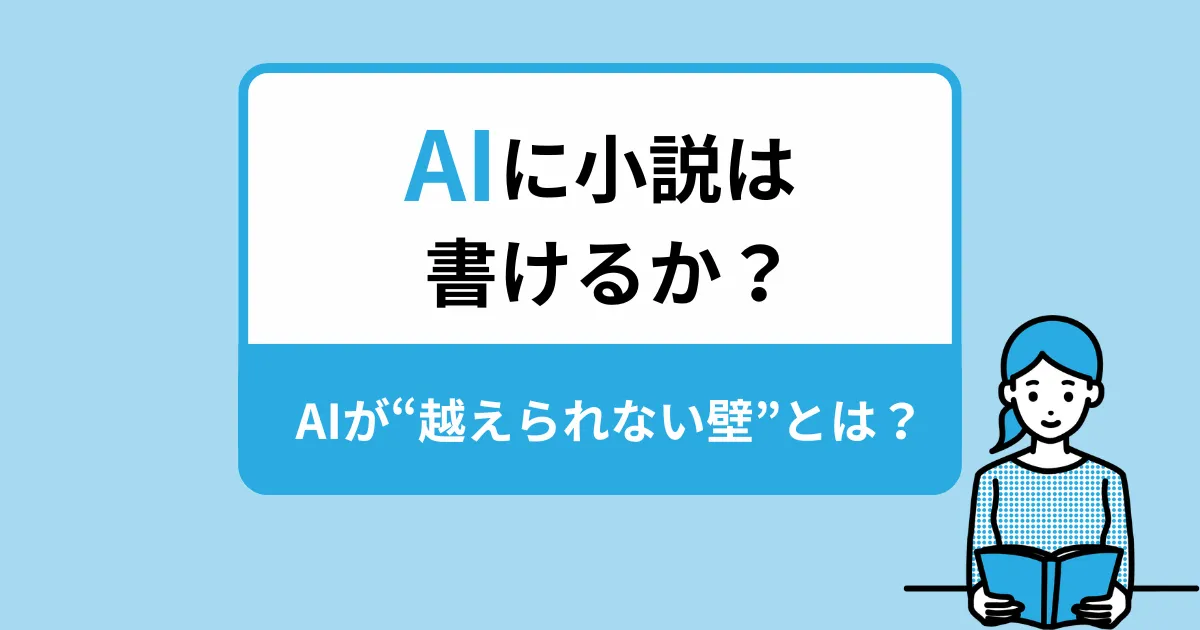
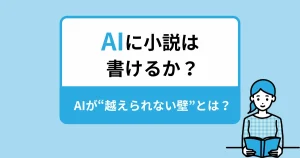
コメント